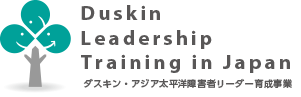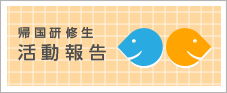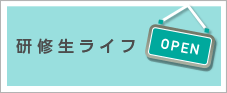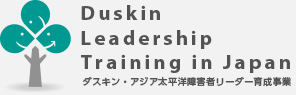- HOME
- 帰国研修生情報
- 活動報告
- フォローアップ研修を実施しました
- 第2期生 ガルーさんの発表内容
活動報告
第2期生 ガルーさんの発表内容
皆さん、こんにちは。皆さん、初めまして。
先にお詫びしておきますが、私が来日していたのは、もう22~23年も前のことなので、日本手話を忘れているところもありますが、どうぞよろしくお願いします。
私はガルーと言います。インドネシアから参りました。ダスキン第2期の研修生です。
日本に研修に来た当初の目的は、1つ目が、日本の聴覚障害児についての情報と聴覚障害における心理学の知識の習得。2つ目が、リーダーシップスキルの向上。3つ目が、日本の社会活動に参加して、日本文化に対する知識を深めること。4つ目が、障害者問題の解決のため知識や技術を向上させること。そして、5つ目が、日本とインドネシアの障害者の現状を比較するというものでした。
日本では、23年前、色々なところで研修させていただいて、インドネシアに様々な知識を持ち帰ることができました。そして、帰国後、どんな活動をしてきたかと言いますと、 帰った後、すぐに活動ができたかというと、そうではありません。様々な問題がありました。インドネシアは、とても広いのですが、その広い国の政府の中に、誰一人として、ろう教育について十分に理解している人はいませんでした。ですから、手話の重要性についても、なかなか理解が得られないというのが、帰国直後の状況でした。ろうの子どもたちの教育は、口話が主体で進められていました。手話ではなく、書記言語が大切だという考え方です。ろうの子どもたちも学校に通っていますが、手話での情報は一切提供されていませんでした。インドネシアは、16万ぐらいの島々があって、600~700もの多様な言語が使われており、同様に手話も多様な手話が使われていることもあり、非常に難しい課題でした。
ろうの子どもたちの学力については、手話で学ぶ機会があり、勉強した人と、手話で学ぶ機会がなく、勉強した人を比較すると、後者の学力は伸び悩んだというデータが残っています。インドネシアの数あるろう学校の中で、2校だけが手話で教育を行っています。 バリ島にあるスシュルサろう学校と私が運営するヒジャビ・ホームスクーリングです。
私がインドネシアに戻って、最初に行ったのは、日本人とインドネシア人、ろう者、聴者が集まるボランティア団体の立ち上げでした。そこから2018年まで、その団体でろう者の権利擁護の活動やろう者のサポート、手話による手話指導、また、政府との交渉など、様々な活動を続けてきました。
2008年、オーストラリアの大学院から連絡をいただき、ろう教育について学ぶ機会をいただきました。そこで3年学びました。
これは、インドネシアにある私たちが立ち上げたろう学校です。初めてのろう学校リトルヒジャビホームスクーリングです。リトルヒジャビの手話は、このように表します。この表現は、「子どもたちにとって悪い影響から守る」という意味が込められています。子どもたちにとって良い教育環境は家庭で、そして、良い先生は、両親だと思うのです。子どもたちが家庭で過ごす時間は長いですから、学校と連携していくことが大切です。
親御さんと共に手話やろう文化を学んでいくことで、将来的に知識や様々な能力を養うことができるようになります。リトルヒジャビは、一般的なろう学校ではなく、家庭支援センターに近いと思います。リトルヒジャビは、マナー教育に重きを置いた教育をしています。それは、イスラム社会での道徳やマナーをきちん学び、身に付けることは、ろう者が聴者と齟齬なく、スムーズにコミュニケーションを取るために大切だと考えているからです。お互いを尊重するためのマナー習得を目指しています。それは、その後の自主性や自立した行動にも繋がっていきます。
子どもが生まれて、その子が、ろうだと分かったら、早期に手話の環境を整えるということが大切です。 幼少期の親子間の会話は、とても大切です。手話の環境の中で育っていくと、子どもの言語能力が向上します。
インドネシアは数多くの島が連なる国ですので、各島々に私が直接出向き、こういったお話ができるといいのですが、それは難しく、また、オンラインでも、インフラが整っているところばかりではありません。スマートフォンも、皆が持っているというわけではありません。そこで、皆で相談して、企業などのサポートも受けながら、私たちの教育方針を伝えるためのボードゲームを作りました。これはバイリンガル(インドネシア語/手話)で楽しめるボードゲームです。現在、約1000セットのボードゲームが各地に送られて、使用されています。
インドネシアは、イスラム教なのですが、手話のコーランはありません。ろうの子どもたちに大切な教えを伝えるために、イスラム教の教えに関する手話の辞典も作りました。
私の今後の計画としては、ろう学校と普通校、そして、社会が連携して、1つの目標のために様々な教育や学び、例えば、手話は何なのか、ろう文化とはなんなのか、親子間のコミュニケーション方法など、共に協力し合い、互いに学び合えるようなワークショップを開催したいと考えています。
この左上の写真の場所(リトルヒジャビ)で、ろう者、聴者(保護者)が一緒に遊びを通して、その意識や考え方を変えられたらと思っています。
下の写真は、手話に興味を持っている聴者の学校関係者に手話を勉強してもらっている様子です。
本当に、色々なことをお話ししたいのですが、なかなか伝えきれません。
私が感謝の気持ちを込めて作ったこの写真のフィギュアフレームを贈りたいと思います。
ダスキン愛の輪のおかげで本当にいろんな方々との出会い、 日本に来て学ぶことができました。インドネシアもどんどん変わっていっています。ダスキンだけではなく、日本にいるご支援いただいた皆さんのおかげで、色々な知識や経験を持ち帰ることができました。 また、これからも、一緒に頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました。